
Credit - Huntstock/Getty Images
DDTは1874年に初めて合成が報告された後、1939年になってスイスの化学者ミュラーが殺虫作用を発見、マラリアやチフスの拡大防止に貢献したことで1948年、ミュラーにノーベル化学賞をもたらしました。その後DDTは、安価な農薬として農地や森林に大量に散布されるようになりましたが、カーソンは1962年に出版した『沈黙の春』で、DDTをはじめとする農薬が環境中に残留し生態系の破壊をもたらす危険性について強い警告を発しました。ベストセラーとなった同書は当時の環境運動に大きな影響を与え、1972年には米国で農薬としての使用が禁止されました。同様の動きは世界各国にも広がり、2001年に採択された残留性有機汚染物質に関するストックホルム条約でもDDTの使用が規制されています。
しかし、カーソンの主張に対しては当初から反対意見があり、近年は「DDT使用規制のせいで開発途上国でのマラリア流行を防げず、数百万人が命を落とした」としてカーソンを殺人者呼ばわりする声すら高まっています。先にDDTの新しい結晶多形についてAngewandte Chemie International Edition (ACIE) で報告したニューヨーク大学のMichael Ward, Bart Kahr両教授らは、DDTの功罪を再評価し、カーソンとその批判派の主張の是非を検討するエッセイを同誌で発表しました。
 エッセイを読む J. Yang, M. D. Ward, B. Kahr, Abuse of Rachel Carson and Misuse of DDT Science in the Service of Environmental Deregulation. Angew. Chem. Int. Ed. 2017, 56, 10026. (2017年8月18日現在無料公開中)
エッセイを読む J. Yang, M. D. Ward, B. Kahr, Abuse of Rachel Carson and Misuse of DDT Science in the Service of Environmental Deregulation. Angew. Chem. Int. Ed. 2017, 56, 10026. (2017年8月18日現在無料公開中)
紹介記事 Fake News and Chemistry: From DDT to Climate Change (June 22, 2017, Chemistry Views)
このエッセイで著者らは、一貫してカーソンの主張を支持しています。DDTが害虫駆除に有効なのは事実ですが、その効果は一時的で、使用を続ける間に害虫が耐性をもつようになるため効果を失うことが知られています。実際、WHO(世界保健機関)は保健衛生の目的に限定してDDTの使用を推奨していますが、害虫に耐性をもたせないために他の殺虫剤と交互に用いるべきとしています。著者らは、DDTはかつて信じられていたような魔法の薬ではなく、せいぜいさまざまな方法の組み合わせによる感染症対策のひとつのピースに過ぎないと考えます。同時に、カーソン自身も感染症対策のための殺虫剤使用を否定しておらず、その過剰な使用に反対しただけだとしています。
さらに著者らは、カーソンへの批判派がDDTの安全性の根拠として今も頻繁に引用する「DDTを添加した餌を与えられたキジでは、そうでないキジよりも卵の孵化率が高まった」という1956年の報告を再検討し、批判派が元データに対して恣意的な操作を行っていることを指摘します。著者らは、『沈黙の春』が環境政策に影響を与えることができた時代には、科学と科学者が一般国民から信頼を得ていたのに対して、そのような信頼が低下した現代ではカーソンに対する科学的根拠を欠いた中傷がはびこるようになったと指摘してエッセイを締めくくっています。



 ChemistryViews (無料ニュースサイト)
ChemistryViews (無料ニュースサイト) Facebookページ: Chemistry by Wiley
Facebookページ: Chemistry by Wiley ワイリー・ヘルスサイエンスカフェ(医学・看護学・獣医学ブログ)
ワイリー・ヘルスサイエンスカフェ(医学・看護学・獣医学ブログ) 電子プラットフォーム Wiley Online Library
電子プラットフォーム Wiley Online Library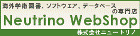 Neutrino WebShop(株式会社ニュートリノ)
Neutrino WebShop(株式会社ニュートリノ) オーヴィス株式会社(理工洋書専門書店)
オーヴィス株式会社(理工洋書専門書店)